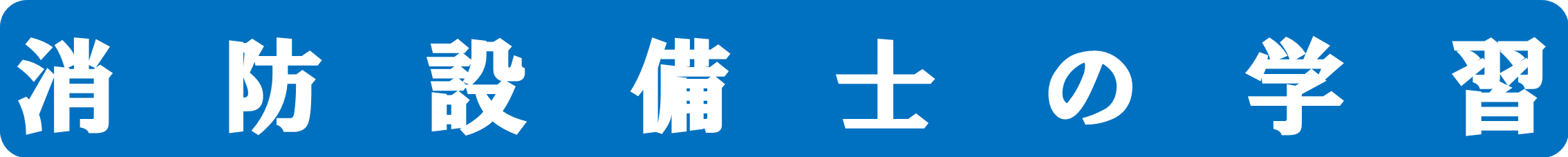救助隊に必要な資器材とは?特別救助隊、高度救助隊、特別高度救助隊が必要な都市とは?救助隊の基準を知ろう!
救助隊とは、火災や事故、自然災害などのあらゆる災害に対して、救助に関する高度な知識と技術、また特殊な資器材等を使用し、救助を必要とする人々を助ける部隊です。現在ではほとんどの消防本部に配置されており、消防士と言えば「オレンジ色の救助隊」と認知されているぐらい人気のある部隊でもあります。
そんな救助隊の根拠となり得る資器材や救助隊が必要となる都市の規模について説明します。
⇒ 特別高度救助隊ってなに?1分でわかるシリーズ、救助隊より凄い?、自治体ごとの違い、どうやったらなれるの?
⇒ ハイパーレスキューってなに?1分でわかるシリーズ、部隊の種類、他の特別高度救助隊との違い、どうやったらなれるの?
救助隊等に必要な資器材とは?
まず救助隊とは、人命救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成され必要な資器材を救助工作車に積載している必要があります。詳しくは、消防法第36条の2において、「市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。」とされており、これが救助隊の根拠になります。
この法令を補完する基準として、「昭和61年自治省令第22号_救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」で詳しく定められており、そこで詳しい資器材の種類も示されています。
救助隊について⇒ 救助隊ってなに?1分でわかるシリーズ、正式名称、様々な消防の特殊部隊、消防隊との違い、どうやってなるのか、法令根拠について
救助隊に必要な資器材
1.一般救助用器具
かぎ付はしご、三連はしご、金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご、空気式救助マット、救命索発射銃、サバイバースリング又は救助用縛、ばく帯、平担架、ロープ、カラビナ、滑車
2.重量物排除用器具
油圧ジャッキ、油圧スプレッダー、可搬ウィンチ、ワイヤロープ、マンホール救助器具、※救助用簡易起重機
3.切断用器具
油圧切断機、エンジンカッター、ガス溶断器、チェーンソー、鉄線カッター
4.破壊用器具
万能斧、ハンマー、携帯用コンクリート破壊器具
5.検知・測定用器具
※※※生物剤検知器、※※※化学剤検知器、※※※可燃性ガス測定器、※※有毒ガス測定器、※※酸素濃度測定器、※※放射線測定器
6.呼吸保護用器具
空気呼吸器(予備ボンベを含む。)、※空気補充用ボンベ
7.隊員保護用器具
革手袋、耐電手袋、安全帯、防塵メガネ、携帯警報器、防毒マスク、※※化学防護服(陽圧式化学防護服を除く。)、※※陽圧式化学防護服、※耐熱服、※※放射線防護服(個人用線量計を含む。)
8.検索用器具
※※簡易画像探索機
9.除染用器具
※※除染シャワー、除染剤散布器
10.水難救助用器具
潜水器具一式、流水救助器具一式、救命胴衣、水中投光器、救命浮環、浮標、救命ボート、船外機、水中スクーター、水中無線機、水中時計、水中テレビカメラ
11.山岳救助用器具
登山器具一式、バスケット担架
12.その他の救助用器具
投光器一式、携帯投光器、携帯拡声器、携帯無線機、応急処置用セット、※車両移動器具、その他の携帯救助工具
一 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。
二 ※※印のものは、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。
三 ※※※印のものは、特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。
四 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。
以上のものを積載することの出来る救助工作車その他の消防用自動車を1台備えることとなっています。
特別救助隊に必要な資器材
先に挙げた救助隊の資器材の他に以下の資器材が必要となります。
1.重量物排除用器具
マット型空気ジャッキ一式、大型油圧スプレッダー、※救助用支柱器具、※チェーンブロック
2.切断用器具
空気鋸、大型油圧切断機、空気切断機、※コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー
3.破壊用器具
削岩機、ハンマドリル
4.呼吸保護用器具
酸素呼吸器(予備ボンベを含む。)、簡易呼吸器、防塵マスク、送排風機、※エアラインマスク
5.隊員保護用器具
耐電衣、耐電ズボン、耐電長靴、※特殊ヘルメット
6.その他の救助用器具
緩降機、ロープ登降機、※救助用降下機、発電機
一 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。
二 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。
以上のものを積載することの出来る救助工作車その他の消防用自動車を1台備えることとなっています。
高度救助隊に必要な資器材
先に挙げた救助隊及び特別救助隊の資器材の他に以下の資器材が必要となります。
1.高度救助用器具
2.画像探索機
3.地中音響探知機
4.熱画像直視装置
5.夜間用暗視装置
6.地震警報器
※7.電磁波探査装置
※8.二酸化炭素探査装置
※9.水中探査装置
※※10.検知型遠隔探査装置
一 ※印のものは、高度救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。
二 ※※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。
三 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。
以上のものを積載することの出来る救助工作車その他の消防用自動車を1台備えることとなっています。
特別高度救助隊に必要な資器材
必要な資器材は、先に挙げた高度救助隊と同等になりますが、特殊車両を備える必要があります。それは、特殊災害対応自動車が必須であり、地域の実情に応じてウォーターカッター及び大型ブロアーを備えることとなっています。
救助隊等が必要になる都市や規模とは?
救助隊の根拠については、先に述べた通りですが、同じ法令及び告示の中で、救助隊を設置する都市についても定められています。
救助隊について⇒ 救助隊ってなに?1分でわかるシリーズ、正式名称、様々な消防の特殊部隊、消防隊との違い、どうやってなるのか、法令根拠について
救助隊が必要な都市や規模とは??
救助隊の設置基準について、原則は消防署の数だけ救助隊を配置することとなっています。ここで言う消防署の数は出張所等を含めず本部(本署)の数と判断して良いと思います。なので、市町村等の規模に関わらず基本的には各消防本部に1隊は救助隊があることになります。ただし、事案の発生状況・人口・管内面積や地形・全ての状況を考慮し増減しても良いとなっているため、救助隊がない消防本部も存在します。また、この増減については以降の特別救助隊、高度救助隊、特別高度救助隊についても同様です。
特別救助隊が必要な都市や規模とは?
特別救助隊は、
①人口が10万人以上で消防本部がある都市では、以下の各号の数プラス1隊必要とされています。(端数切捨て)
1.人口10万人を超えて100万人までの都市は、人口を15万で割った数
2.人口100万人を超えて300万人までの都市は、人口を30万で割った数
3.人口300万人を超える都市は、人口を40万で割った数
②人口が10万人未満で消防本部がある都市では、中高層建築物、幹線道路、鉄道、空港、危険な作業を伴う事業場等に係る人命の救助が特に必要であると判断した場合も必要となります。
①に該当する場合は、救助隊のうち必要数を、②に該当する場合は、救助隊のうち1隊以上を特別救助隊とすることとなっています。
高度救助隊が必要な都市とは?
高度救助隊は、
①特別区が連合している都市
東京
②地方自治法第252条の19第1項で指定されている都市(政令で指定されている人口50万人以上の市)
大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市
③地方自治法第252条の22第1項で指定されている都市(政令で指定されている人口30万人以上の市)
宇都宮市、金沢市、岐阜市、姫路市、鹿児島市、秋田市、郡山市、和歌山市、長崎市、大分市、豊田市、福山市、高知市、宮崎市、いわき市、長野市、豊橋市、高松市、旭川市、松山市、横須賀市、奈良市、倉敷市、川越市、船橋市、岡崎市、高槻市、東大阪市、富山市、函館市、下関市、青森市、盛岡市、柏市、西宮市、久留米市、前橋市、大津市、尼崎市、高崎市、豊中市、那覇市、枚方市、八王子市、越谷市、呉市、佐世保市、八戸市、福島市、川口市、八尾市、明石市、鳥取市、松江市、山形市、福井市、甲府市、寝屋川市、水戸市、吹田市、松本市、一宮市
④消防庁長官が指定する消防本部
現在のところ、なし
①~④に該当する都市は、特別救助隊のうち1隊以上を高度救助隊とすることとなっています。
特別高度救助隊に必要な資器材
特別高度救助隊は、
①特別区が連合している都市
東京
②地方自治法第252条の19第1項で指定されている都市(政令で指定されている人口50万人以上の市)
大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市
①及び②に該当する都市は、高度救助隊のうち1隊以上を特別高度救助隊とすることとなっています。
まとめ
今回は、救助隊に必要な資器材及び救助隊を設置しなければならない都市について説明しました。なんとなく大きな消防本部には救助隊があると言う認識の方もいたのではないでしょうか。全ては法律で明確に定められており、その上で各自治体の状況によって救助隊があったりなかったりしています。そういった目線でなぜこの消防にはこの隊があるんだろうなんて考えてみるのも面白いかもしれません。
よく読まれている記事一覧
» 【消防士を目指す】取っておくと有利な資格はある?資格はいらない?危険物取扱者、消防設備士、防災士など消防に関する資格を知ろう!
» 【消防士を目指す】救助隊を目指すならこの資格を取るべし!救助隊になるために使える資格5選!
» 【消防士を目指す】予防で役に立つ!予防業務で使える資格10選!
» 【消防士を目指す】こんな資格もおすすめなの?消防士で使える意外な資格10選!
カテゴリー一覧
» 消防法の解説
» 消防用語集
» 消防設備士の学習
» 全国の消防組織
» 消防の予防を学ぶ
» 防災を学ぶ
» 建築と消防